食中毒を予防しよう
腸管出血大腸菌(O157等)感染症予防のポイント
O157等による感染症は、一般に夏から秋にかけて多く発生しますが、食中毒等の場合には時期を問わず一時期に大量に患者が発生することもあります。
O157等の経口感染症や食中毒を未然に予防するには、清潔・加熱・迅速の3原則を守ることが重要です。家庭はもとより、野外において飲食等する場合にも注意しましょう。
感染経路
食品に付着した菌が直接口に入る場合のほかに、トイレの取っ手やドアノブ等に付着した菌が手を介して口に入る場合もあります。
症状
多くの場合は、感染してから3~5日あとに腹痛や水様性の下痢をおこし、後に出血性の下痢となることがあります。
成人では感染しても症状が出なかったり、軽い下痢だけの場合が多くありますが。小さいお子さんやお年寄りは重症になる場合があるので注意が必要です。
予防対策1
日頃からよく手を洗い、消毒する習慣を身につけましょう
- トイレの後、調理するとき、食事の前には、よく手を洗いましょう。
- 水道の蛇口にも細菌が付着している可能性があるので、できるだけ消毒を心がけましょう。
予防対策2
食べ物は十分に洗い、できるだけ加熱してから食べましょう
- 牛肉などの食材は中心部まで十分に加熱してから食べましょう(中心温度が75℃1分以上加熱すれば細菌を殺すことができます)。
- 生野菜は十分な水道水(消毒した井戸水)でよく洗いましょう。
予防対策3
調理後できるだけ早く食べましょう
- 加熱調理した食べ物でも、時間が経つと細菌が付着・繁殖するので早く食べましょう。
- 冷蔵庫の過信は禁物です。調理後は早く食べましょう。
胃腸を弱めていたり、体力が低下すると、病気にかかりやすくなります。十分な睡眠とバランスのとれた食事をとるなど規則正しい日常生活を心がけましょう。
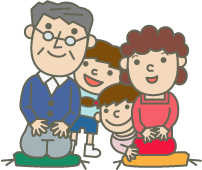
- この記事に関するお問い合わせ先
-
元気わくわく健康課 保健指導係
〒939-0642 富山県下新川郡入善町上野2793-1
電話番号:0765-72-0343
ファックス:0765-72-5082
メールフォームによるお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-






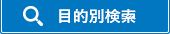



















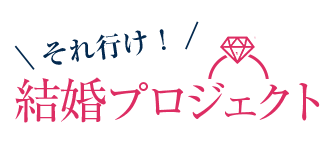
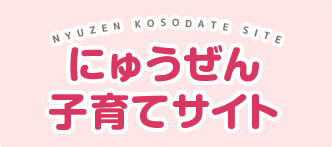
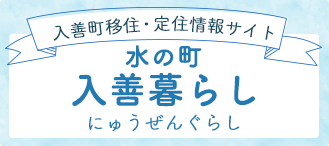






更新日:2021年02月01日