記念物~天然記念物~
1.杉沢の沢スギ 昭和48年8月4日国指定

沢スギ
かつて、黒部川扇状地の末端部で、小川が流れ地下水の湧出する海岸に近い地域に、スギの多い林が発達していました。そして、その場所を杉沢、そこに生えているスギを沢スギと呼んでいました。
このような杉沢は、かつて下飯野新から春日の間の黒部川旧河道に沿って、筋状か点状に分布し昭和29年に約40か所、約130ヘクタールありました。しかし、昭和48年ごろの圃場整備事業で、これらの杉沢は水田化されることになりました。現在残っている、吉原柳原地区2.67ヘクタールの杉沢もその対象でしたが、平地の湧水地帯に生育する自然林に近い杉林は全国的にも非常に珍しく、多くの人々の活動によって保存することに決まりました。
昭和48年には国の天然記念物に指定され、さらに昭和60年には全国名水百選にも認定され、全国的に知られるようになり、多くの自然愛好家が訪れようになりました。
2.沢スギの特徴
沢スギの維持は間伐による人工更新です。このスギは根本からの萌芽(ほうが)性がつよく伏条性があり、枝の発根力の良い特性があります。このため、一株から何本もの幹が出ます。間伐するとき、その株の主幹を伐り、次に大きいものを育てて、順次間伐する更新法で、いわば大きい古株(親株)からできあがった杉林です。
また、杉株の根本に萌芽の幼芽が何本か生育して、大きくなると積雪の重みで倒れ、毎年繰り返していると側方に曲がり、成長と共に先端が上向します。そしてそれ自体の重さで、曲がった部分が着地し、そこから発根して成長を始めます。このような伏条現象は、日本の平地では、この沢スギ林ただ一ヶ所です。
また特記すべき事項として、平地で水湿地に生育するスギは日本でも杉沢の沢スギだけということが挙げられます。では、なぜ杉沢の沢スギだけが特別なのでしょうか?それは、林内が湧水の影響で冬も比較的暖かいからだと考えられます。
3.沢スギ林の植物
林内には沢スギだけでなく、タブノキ、アカガシ、ユズリハ、マンリョウ、カラタチバナ、オモト、オオキジノオシダなど暖地性の植物が多くみられます。そのほか、洪水等の流水で運ばれたと思われるノリウツギ、アケボノシュスラン、ヤマドリゼンマイ、ヤマイヌワラビ、トウゲシバ、ショウジョウバカマ、ヤマザクラ、オククルマムグラ、ケナシヤブマデリなどの山地性の植物、湿地性、陰地性のシダ植物やコケ植物なども多くみられます。
ナミウズムシ、カワゲラ類、トミヨなどの水生動物もいます。
昆虫類は、県内ではこの杉沢で発見されたクロハグルマエダシャクとキアシツヤヒラタゴミムシ、平地には珍しいシマアメンボなどを含めて約120種類が知られています。
散歩がてらに、是非「杉沢の沢スギ」を訪れてみてください。
沢スギ自然館のご利用について
開館時間
午前9時~午後5時(午後4時30分までにご入館ください)
休館日
毎週月曜日(祝日の場合は翌日)
祝日の翌日 冬季(12月28日~2月末日)
館内整理日(あらかじめお知らせします)
富山県下新川郡入善町吉原950番地 電話 0765-72-1710
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育委員会事務局 男女共同参画・文化係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-3858
ファックス:0765-74-2790
メールフォームによるお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-






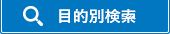



















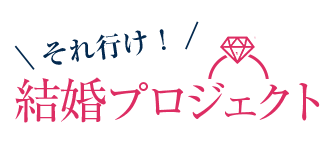
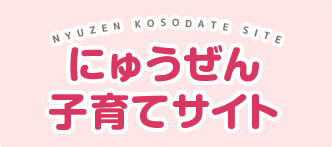
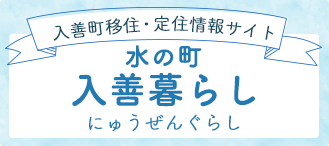






更新日:2021年02月01日