塞の神まつり
| 開催日 | 1月第2日曜日(1月15日が日曜日の場合は15日) |
|---|---|
| 開催場所 | 入善町上野・邑町地区 |
| 交通案内 | あいの風とやま鉄道入善駅より車で5分 |
1 文化財の概要
平成22年1月15日、国の文化審議会において、入善町上野(邑町地区)に伝わる「塞の神まつり」が、「邑町のサイノカミ」として国の重要無形民俗文化財指定の答申を受けました。
- 指定名称 邑町(むらまち)のサイノカミ
- 所在地 富山県下新川郡入善町上野(うわの)(邑町地区)
- 保存団体 塞(さい)の神まつり保存会
(高森 学会長、約120戸から成る邑町地区の住民約270名により組織) - 指定の理由(文化庁発表の文化財の特色と文化財の説明)
文化財の特色
本件は、年頭にあたって大火を焚き、災厄を払う小正月の火祭りの典型例の一つであり、年齢階梯的な子どもの集団を中心に執り行われ、各家をめぐった人形を村境で灰になるまで燃やすなど地域的な特色がある。
文化財の説明
本件は、富山県東部に位置する入善町上野の邑町地区で行われる、厄払いや無病息災、五穀豊穣を祈願する小正月の火祭りの行事である。
早朝より、子どもたちが、家々を訪問して正月飾りを集め、菓子や米などをもらう。このときオヤカタと呼ばれる最年長の子どもはデクという男女一対の木製の人形をもち、他の子どもは玄関先でサイノカミの唄を歌う。
子どもたちが各家を回っている間、地区の境では竹と藁で円錐形の作り物が作られる。子どもたちが回り終えた後、デクを正月飾りとともに作り物の中に納めて火をつける。このとき竹の節のはじける音が大きいほど災厄が払われるという。火が下火になると、燃え残ったデクを探し出して完全に灰になるまで燃やす。
我が国における小正月行事の変遷を考える上で重要である。
2 「邑町のサイノカミ」の概要
- 入善町上野の邑町地区の子どもたちが、木製の男女一対の人形を持って各戸を勧進し、その人形を燃やして一年の防塞を祈願する小正月行事。
- 行事では、小学生の男子が「デクサマ」(木製の男神と女神)を持ち、サイノカミの唄を歌いながら集落内の各家庭を回り、正月飾りと米や大豆・小豆等を集める。その後、青竹や藁で高く組まれた作り物に、人形と正月飾りなどを納め、灰になるまで燃やしやる。
- かつては小正月にあたる1月15日に行われていたが、現在は1月第2日曜日に催行されている。(ただし、1月15日が日曜日の場合は1月15日)
3 指定の意義
- 国の重要無形民俗文化財として指定されることにより、入善町の知名度があがるとともに、改めて地域にある伝統文化を見直し、文化財保護の契機につながる。
- 地区住民の協力のもとに子どもたちによって継承されている行事であり、地域への愛着がさらに深まるとともに、郷土の誇りの醸成に繋がる。
4その他
- 今回の指定により、富山県内の国指定重要無形民俗文化財は7件となる。
- 県内の国指定・選定文化財の総件数は、合計で104件となる。
- 入善町では、国重要無形民俗文化財の指定は初めてである。
- 町内には合計3件の国指定・登録の文化財があり、本件により町内では4件目となる。
国指定の天然記念物:1件(杉沢の沢スギ・昭和48年指定)
国指定の史跡:1件(じょうべのま遺跡・昭和54年指定)
国登録の有形文化財(建造物):1件(下山芸術の森・発電所美術館・平成8年登録) - 平成22年は1月10日(日曜日)に行われた。

塞の神石碑

邑町地区の家々をまわる子供たち(小学生)

正月飾り・米・大豆・小豆などを集める

竹とわらで角錐の作り物が作られる

男女一対の「デクサマ」を、わらで包んで中に入れる

集めた正月飾りなどを作り物の周りに積み、火がつけられる

煙を上げ燃える作り物

火をつけた後、「さいのかみじゃ…」と子供たちの歌が始まる。

燃え残ったデクを探し出して完全に灰になるまで燃やす
参考【塞の神の歌】
さいのかみじゃ おおかみじゃ
じいにも かあにも ぼくぼくじゃ
らいねんもきゃ じゅうさんじゃ
にょうぼう うんだら しょうぶした
おとこうんだら そ そ そだて
お問合せ先:入善町教育委員会事務局 文化係
電話:0765-72-1100 (内線355) ファックス:0765-74-2790
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育委員会事務局 男女共同参画・文化係
〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳423
電話番号:0765-72-3858
ファックス:0765-74-2790
メールフォームによるお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-






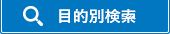



















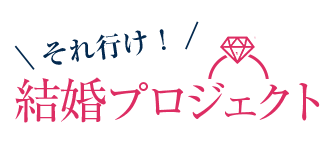
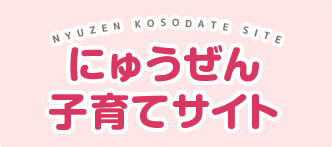
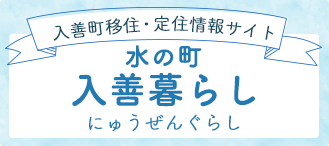






更新日:2022年06月09日